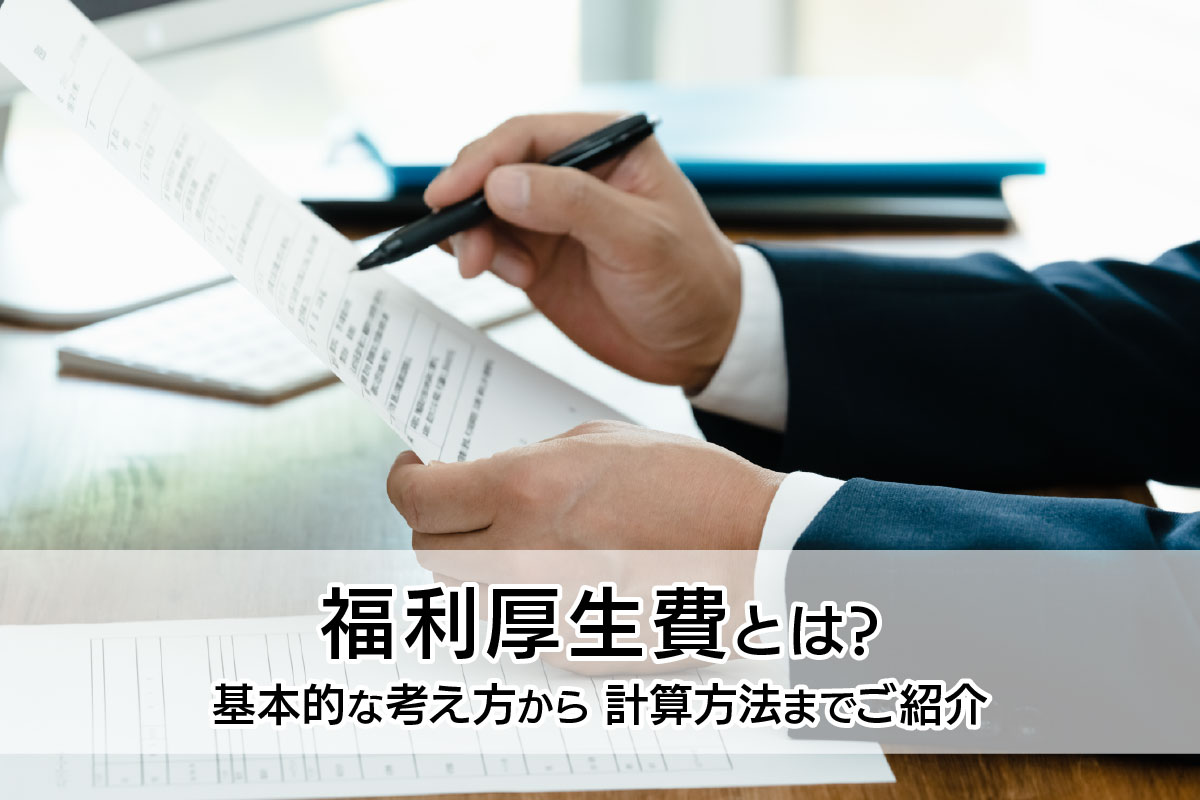福利厚生としての英会話|企業が導入するメリットとデメリット・費用計上の条件まとめ
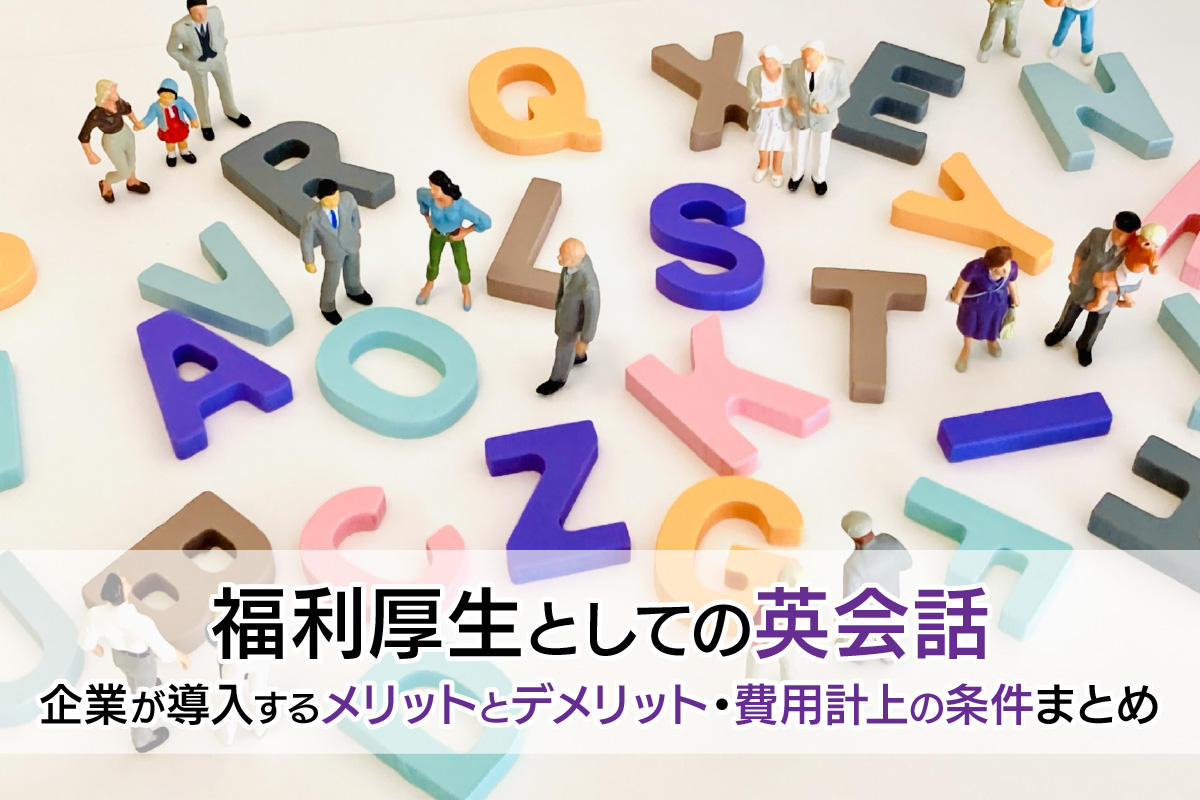
「英語を使える人材を育てたいけど、英会話を福利厚生として導入できるのかな?」
「英会話を導入したいが、自社にとってどの程度メリットがあるのかわからない」
グローバル化が進む現在、英会話の重要性はますます高まっており、福利厚生として英会話を導入する企業が増えています。その一方で、福利厚生費として計上するために満たすべき条件や、社員にとってどの形態が適しているかが課題になるケースもあります。
そこで本記事では、英会話を福利厚生として導入する際の企業側・社員側双方のメリットとデメリットを詳しく解説します。また、福利厚生費として計上するための条件や、利用できる英会話サービスの形態などもお伝えするので、ぜひ最後までご覧ください。

目次
1.福利厚生で英会話が注目されてきている理由
![]()
英会話は現代のビジネスにおいて重要なスキルです。多くの企業がその価値を認識し、従業員の英語スキルの向上を図る取り組みを強化しています。
一般社団法人国際ビジネスコミュニケーション協会の「英語活用実態調査2019 企業・団体 ビジネスパーソン 2019」によると、「今後のビジネスパーソンにとって重要な知識やスキル」として82.6%の企業が「英語」を選択しています。
また、同調査での「実施している英語教育施設」という質問では、「研修機関からの講師派遣による社内研修」が51.9%を占めていました。「海外への研修派遣」と回答した企業が35.0%もあることも注目ポイントです。
さらに、ジェトロ調査部国際経済課が発表した「2024年度 日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査」では、2025年の海外売上高について、前年度比で「増加」すると予想する企業の割合が全体の56.8%もあることが明らかになりました。
そして、海外拠点を持つ企業の47.9%が「さらに拡大を図る」、海外拠点を持たない企業の40.8%が「新たに進出したい」と答えています。
このように、多くの企業が海外事業の拡大を視野に入れており、ビジネスパーソンにとって英語力が重要なスキルだという認識が広がっています。こうした背景から、企業の人材育成戦略として英語教育への関心が高まっていると考えられます。
2.福利厚生として英会話を導入するメリット
福利厚生として英会話を導入すると、企業側にも社員側にもメリットが期待できます。ここでは、両者それぞれの観点からメリットを見ていきましょう。
![]()
あわせて読みたい
2-1.企業側のメリット
企業側のメリットとしては、以下の3つが挙げられます。
- 採用における他社との差別化
- 事業のグローバル展開
- 社員のモチベーションアップ
2-1-1.採用における他社との差別化
英会話を福利厚生に導入していることをアピールすることで、英語に関心のある優秀な人材の採用につながります。英会話を自主的に学ぼうとしている人にとって、社員教育の一環として英会話が導入されている企業は理想的な環境です。求職者が同程度の規模の企業と比較した際に、英会話学習の福利厚生がある企業は魅力的だと感じられるでしょう。
同じような規模や条件の企業と比較した際に、英会話プログラムがあることは求職者にとって一つの魅力として映ります。また、英語学習に興味のある人材が採用されることで、積極的に研修やレッスンに参加する傾向が強くなり、短期間で英語スキルを向上させる可能性も高まります。こうした学習意欲の高い社員が増えることで、職場での英語を用いたコミュニケーションも円滑になり、多国籍人材の採用や協働も進めやすくなるでしょう。
2-1-2.事業のグローバル展開
自社の事業を熟知した社員が英語力を高めることで、事業のグローバル化にも柔軟に対応できるようになります。新たに英語スキルを持つ人材を採用する負担を軽減し、海外とのコミュニケーション基盤を整えることができるため、より効率的なグローバル展開が可能になるでしょう。
新規雇用の人材は英語力を重視しつつ、現在の社員にも英会話教育を推進することで、より高い効果が期待できます。
2-1-3.社員のモチベーションアップ
仕事に直結するスキルの向上は、社員のモチベーションアップに効果的です。英語教育と自社のグローバル化を推進していくことにより、学んだスキルをビジネスで実際に活用できるため、達成感も高まりやすいでしょう。
この実務での成功体験が、さらなる学習への意欲を生み出し、好循環を作り出します。英語学習の価値を実感した社員は自発的に学び続ける傾向があり、結果として企業が提供する英会話関連の福利厚生も効果的に活用されることになります。
2-2.社員側のメリット
社員側のメリットとしては、以下の3つが挙げられます。
- 採用における他社との差別化
- 事業のグローバル展開
- 社員のモチベーションアップ
2-2-1.企業負担で英会話を学べる
福利厚生で英会話を導入することで、社員は費用を気にせず英語のレッスンを受けられるようになります。自費だとレッスンをためらっていた社員も、企業負担で受けられるようになることで英語学習を始めやすくなるでしょう。
福利厚生で英会話レッスンを行う場合、費用の負担額や内容、還付条件などは企業独自で決定するため、社員側がどの程度のメリットを得られるかは企業によって異なります。たとえば、プログラム修了後に受講費用を還付する方式を採用すれば、受講者に最後までコースを完了する動機付けができるため、挫折を防ぎやすい点がメリットです。
2-2-2.海外案件を担当できるようになる
英会話力が向上することで、社員が海外案件を担当できる可能性が高まります。海外の取引先やグループ会社とのコミュニケーションが円滑になるため、業務の幅が広がり、本人のキャリアアップにもつながるでしょう。
特に、ビジネス英会話を習得することで、これまで苦戦していた商談や交渉でも実力を発揮しやすくなります。また、海外案件を担当すると日常的に英語に触れるようになるため、生きた英語を学べる環境に身を置けるのもメリットです。
2-2-3.業務の効率アップ
英語力の向上は、業務効率の向上にもつながります。英語力が低い状態では、海外向けの文書作成やメール対応にも時間がかかりますが、英語力が上がるとスムーズに進められるようになります。
業務効率が向上すれば、社員自身の評価や達成感も高まり、結果としてモチベーションアップにもつながります。福利厚生での英語レッスンを通じて、身につけたスキルは、業務以外の場面でも社員自身の成長をサポートする効果が期待できます。
3.福利厚生として英会話を導入する企業側のデメリット
英会話レッスンを福利厚生として導入することで、多くのメリットを得られますが、一方でいくつかの課題も想定されます。とくに注意したいのが、任意での受講です。社員の自主性に任せた形になるため、受講をしなかったり、途中で放棄したりすることも珍しくありません。結果として想定していた成果を出せない恐れがあります。
こうした課題を防ぐために、社員が自発的に受講したくなる仕組みを構築することが重要です。英語力向上による業務上のメリットを伝えたり、受講した社員に特典を設けたりするのが効果的です。時間的な制約で受講が難しい社員もいることを考慮して、業務時間内での受講を認めるなどの工夫も検討しましょう。
4.英会話を福利厚生費として計上するための条件
福利厚生で英会話レッスンを導入する場合、福利厚生費として計上できるように事前に確認しておきましょう。経費として計上するためには以下の条件を満たす必要があります。
- 従業員全員が利用可能な状況であること
- 英語学習が業務効率化に寄与すること
- 適切な証拠資料を整備すること
4-1.従業員全員が利用可能な状況であること
![]()
英会話のレッスンプログラムを作成する場合には、全従業員が利用できるように制度を設計しましょう。福利厚生は、役職・雇用形態・年齢・性別などの違いで利用条件を設けると、従業員間での不平等が生じて不合理な待遇差とみなされる可能性があります。すべての従業員が平等に利用できるように考慮しましょう。
4-2.英語学習が業務を効率化させるツール
福利厚生費として認められるには、英語学習が業務の効率化に結び付く合理的な理由を示す必要があります。自社の事業における英語スキルの必要性や、英語力向上による業務効率化の具体例を整理しておきましょう。
たとえば、海外取引先との交渉や、海外との取引や国際的なビジネスに役立つスキルアップは、業務との関連性が認められやすくなります。仮に現在、直接的な国際業務がなくても、将来的な事業拡大の可能性や人材育成の長期的視点から、英語学習の必要性を説明することが可能です。ただし、福利厚生として計上する以上、その内容が事業目的に即していることを明確にする必要があります。
4-3.証拠の提出
福利厚生費として英会話レッスンの費用を経費計上する際は、英会話教室など外部機関利用時の領収書や受講証明書をきちんと保管しておく必要があります。レッスンプログラムの内容が記載された書類や参加者のリストなども必要です。
仮に、利用条件が平等性に欠けていたり、証拠資料が不十分だったり、プログラム内容や業務関連性が説明できなかったりすると、経費として計上できなくなります。不安がある場合は、福利厚生のプロに相談すると的確なアドバイスやサポートを得られるでしょう。
あわせて読みたい
5.福利厚生で利用できる英会話サービスの形態
福利厚生で英会話サービスを導入する場合、社員にとって利用しやすい形態を選ぶことが成功の鍵となります。企業が福利厚生で英語学習を実施する場合、主に以下の形態で行われています。
- 通学型
- 講師派遣型
- オンライン型
5-1.通学型
通学型は、社員が英会話教室に通ってレッスンを受ける形態です。マンツーマンレッスンやグループレッスンがあり、基本的には希望の形態を選べます。予算や理想とする環境に応じて選ぶとよいでしょう。
マンツーマンレッスン
社員が自分のペースで学ぶことができるため、業務で必要なスキルを効率的に習得しやすいです。たとえば、会議での発言練習やプレゼン資料の添削といった、実務に直結した内容を重点的に学べます。
グループレッスン
一般の生徒と一緒に受講するため、他者と関わりながら英語を学ぶことで学習意欲の向上が狙えます。英会話教室によっては、企業別グループレッスンを設定してもらえる可能性もあります。
通学型のデメリットとなるのが、教室まで移動する時間の捻出です。社員が業務と通学を無理なく両立できるよう、交通アクセスの良い教室を選ぶ、勤務時間内でも参加可能にするなど、柔軟な運用を検討しましょう。
5-2.講師派遣型
講師派遣型は、英会話講師を職場に招いてレッスンを行う形態です。従業員が英会話教室に移動する必要がないため、時間を効率的に使えます。また、社内で決まった時間にレッスンが行われるので、業務の調整をして参加しやすいのもメリットです。
社内で実施するため、全員参加を目指す場合にも効果的です。英会話レッスンを優先するように促すと、多忙な社員も積極的に参加しやすいでしょう。
注意点としては、一定の規模を維持するためにも多くの社員に参加を募る必要があります。参加者が少ないとレベル別でプログラムを組みにくくなり、効果的な学習環境を維持しにくくなるでしょう。
デメリットとしては、振替対応が難しい点が挙げられます。一般の英会話教室であれば振替レッスンなどにも対応できるケースが多いですが、講師を自社に招く場合は個別対応での振替は難しいでしょう。業務都合などで欠席すると学習進度に遅れが生じ、その後のレッスンにも支障をきたす場合もあるため注意が必要です。
5-3.オンライン型
オンライン型は、自宅やオフィスなど場所を選ばずインターネットを介して受講ができる形態です。パソコン、スマートフォンの通信機器・通信環境・受講環境は必要ですが、どこでも受講できるのはメリットといえます。在宅勤務をしている社員でも受講しやすく、働き方を問わず利用しやすい点も現代にマッチしています。
自由な時間にオンラインレッスンを利用できるサービスを選んだ場合、社員自身が仕事量やスケジュールと照らし合わせながら受講できるのも魅力です。業務を優先しながらレッスンと両立を図る場合にも有効な方法といえるでしょう。
デメリットとしては、社員の自主性に任せることになるため、受講率が伸び悩むリスクがあります。また、通学型や講師派遣型と比べると受動的になりやすく、モチベーションを維持しにくい可能性があります。
自社が採用している働き方や社風に合わせて、自社にとってどの形態が理想的であるか検討することをおすすめします。
6.最後に|英会話の福利厚生は社員のニーズに合っているのかチェックしよう
英会話を福利厚生として導入することで、企業側・社員側ともにさまざまなメリットが期待できます。特に、国際的な事業展開や社員スキルの底上げを目指す企業にとって、英会話は有力な選択肢の一つです。
ただし、福利厚生を成功させるには、導入する目的が企業の事業方針や社員のニーズとマッチしているかを確認することが重要です。たとえば、英語スキルが業務で必要とされない職種が多い場合や、社員からの関心が低い場合には、導入後の利用率が伸び悩む可能性もあります。そのため、事前に社員の声を聞き、求められるスキルや学習内容を正確に把握することが重要です。
英会話が業務に直結してない部門や職種であっても、英語学習を福利厚生として提供する方法があります。そこでおすすめなのが、「カフェテリアプラン」です。
カフェテリアプランとは、企業が社員に一定のポイントを付与し、企業ごとに設定されたメニューの範囲内で自由に選べる制度です。社員が自分自身でニーズを感じるメニューを選ぶ方式であるため、英会話に関心のある社員がサービスを活用してスキルアップを目指すことができます。
イーウェルでは、カフェテリアプランをはじめ、企業の特色に合わせた福利厚生サービスを提供しています。企業の事業内容に合わせた導入方法など、実践的なプランをご提案可能です。英会話の導入にお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
社内コミュニケーションを活発にし、従業員の働く意欲を高める「インセンティブ・プラス」
ポイントを使って評価や感謝を伝え合うことで社内コミュニケーションを活性化するWEBサービスです。
関連キーワード
Related keywords
関連記事
Related article
おすすめ記事
Recommend