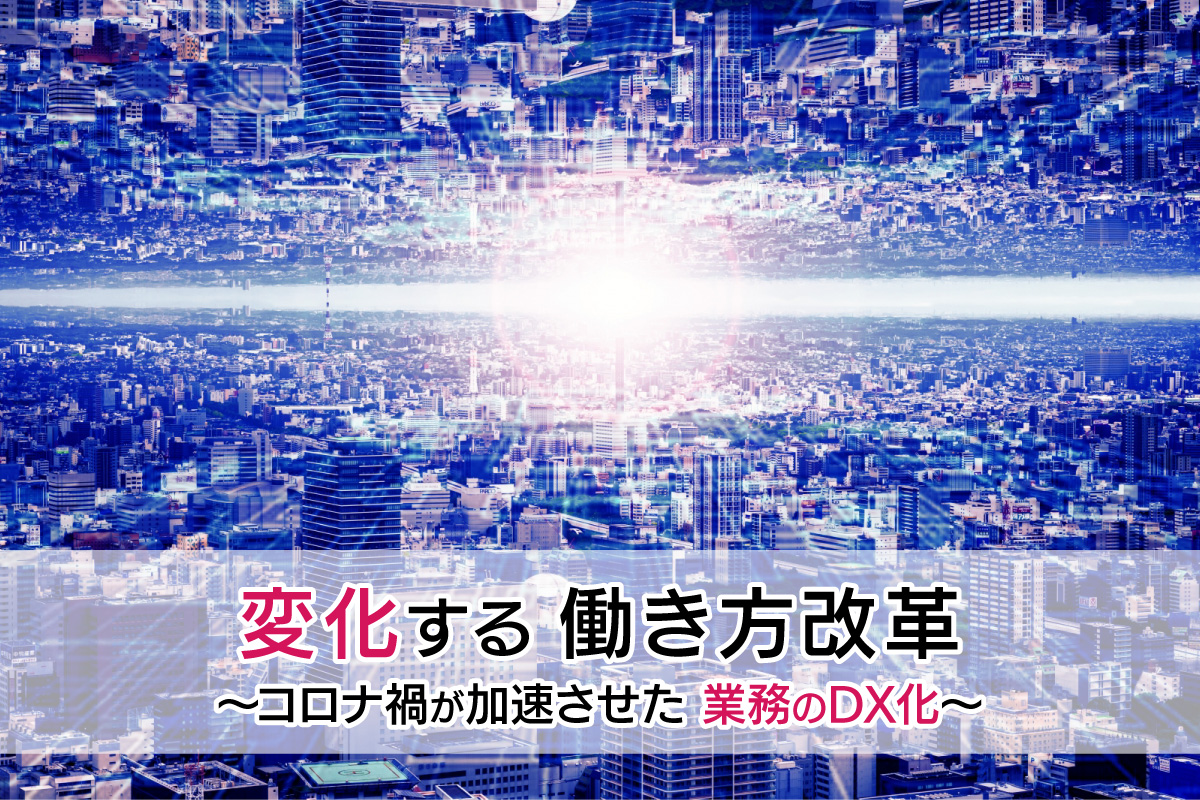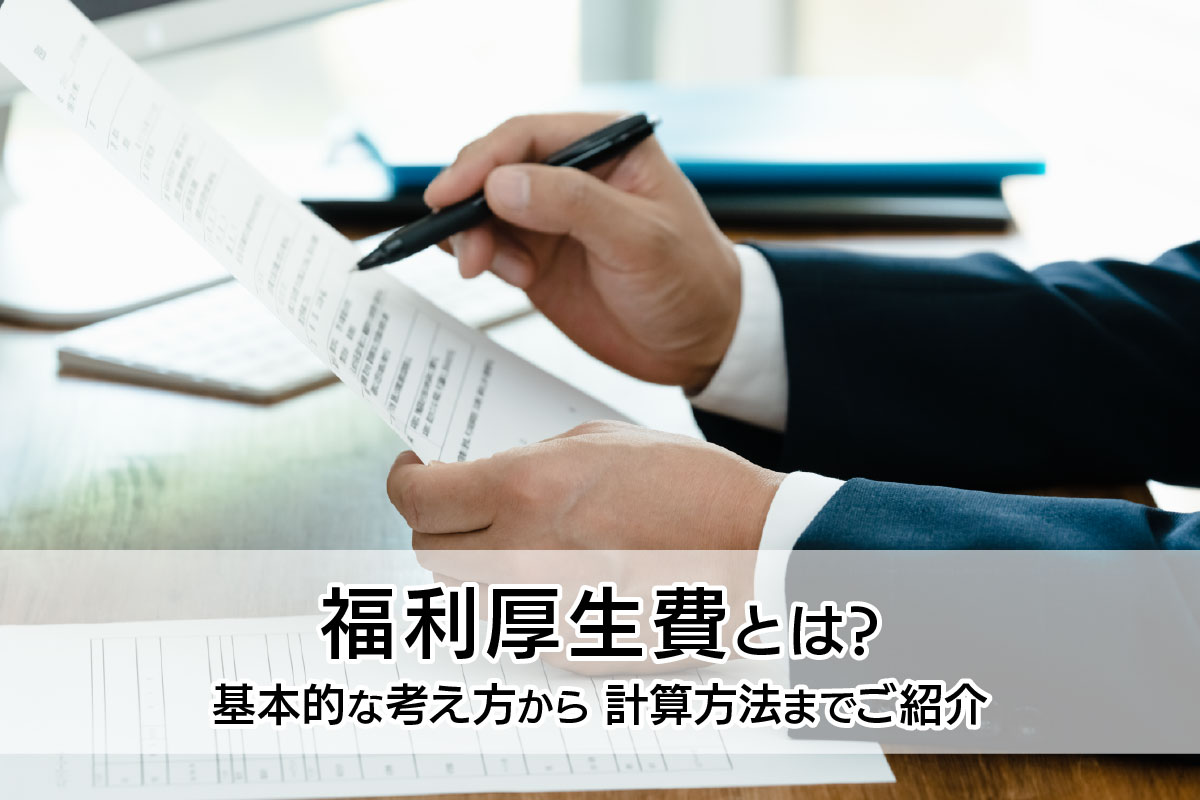従業員満足度を高める福利厚生イベント|アイデアと実施ポイント

「親睦会を開いても参加率が低い」
「従業員が本当に喜んでくれる福利厚生イベントは何なんだろう」
など、福利厚生イベントでお悩みの方もいらっしゃるでしょう。かつては主流だった運動会や社員旅行などのイベントは、近年では規模を縮小している企業が少なくありません。従業員が本当に満足できる福利厚生を実施するためには、従業員一人ひとりのニーズにあった制度に変えていく必要があります。
本記事では、従業員の満足度を高めるための福利厚生イベントのアイデアと実施ポイントを解説します。ぜひ、自社の福利厚生イベントの実施に向けてご活用ください。

目次
- 大企業ほどイベント活動費の割合を大きくしている
- 福利厚生としてイベントを開催するメリット
- 2-1コミュニケーション活性化
- 2-2従業員のモチベーション向上
- 2-3企業文化の醸成
- イベントの具体例とトレンド
- 3-1 社内運動会やスポーツイベント
- 3-2 勉強会や研修イベント
- 3-3 社員旅行やアウトドア活動
- 福利厚生イベントを成功させるポイント
- 4-1 目的を明確化する
- 4-2 参加しやすいスケジュール設定
- 4-3 従業員の意見を反映する
- イベント費用を福利厚生費にする条件
- 5-1 全従業員が対象であること
- 5-2 常識の範囲内の金額設定
- 5-3 現金支給ではないこと
- 福利厚生イベントにおける注意点と対策
- 6-1 換金性の高い景品のリスク
- 6-2 従業員間の不公平感を防ぐ方法
- 6-3 法規制や税務リスクへの対応
- イベント開催に必要な5ステップ
- 7-1 イベントを開催する目的を明確にする
- 7-2 企画案を作成する
- 7-3 従業員に告知して準備する
- 7-4 イベントを開催する
- 7-5 振り返って改善点を次につなげる
- イベント参加率向上のための工夫
- 8-1 事前のアンケートを活用する
- 8-2 参加の義務化を避ける
- まとめ
1.大企業ほどイベント活動費の割合を大きくしている
![]()
従業員の満足度を高める方法の一つに、イベントの実施が挙げられます。「一般社団法人日本経済団体連合会 2019年度福利厚生調査結果」によると、規模の大きい企業ほど文化・体育・レクリエーションの活動への補助に費用を費やしていることがわかります。
例えば、5,000人以上の企業の活動への補助が一人当たり1,513円であることに比べ、500人未満の企業は627円と半額にも満たない金額です。企業規模が大きいほどイベント活動に費やす費用に当てる体力があるといえますが、その投資価値が認められている様子がうかがえます。
1−1.コロナ以降は個別対応やニーズにあった福利厚生が重要
先述の調査は2019年に実施されたものであり、コロナ禍を経た近年では、イベント活動に消極的な企業も少なくありません。企業内での運動会や社員旅行、家族イベントなどは減少傾向にあり、福利厚生でのイベント実施にも予算を削減している企業が少なくないでしょう。
しかし、2019年のデータからもわかるように、イベント活動は決して軽視していいものではありません。従業員が快適に過ごせるような環境をつくるためには、現代のライフスタイルやニーズに応じた新しい福利厚生が求められています。
コロナ以降の特徴といえるのが、ライフスタイルの多様化です。福利厚生において一人ひとりが満足できるサービスを充実させることで、従業員の満足度向上につながるでしょう。
あわせて読みたい
2.福利厚生としてイベントを開催するメリット
![]()
企業が福利厚生としてイベントを開催する場合、どのようなメリットが期待できるのでしょうか。主なメリットは以下のとおりです。
- コミュニケーション活性化
- 従業員のモチベーション向上
- 企業文化の醸成
それぞれのメリットを詳しく見てみましょう。
2−1.コミュニケーション活性化
福利厚生としてイベントを行う場合、コミュニケーションの活性化を目的とする企業が多くあります。普段から業務を一緒に行っている同僚との関わりが深まるだけでなく、他部署と交流する機会にもなるため、新しいコミュニケーションを構築するきっかけにもなるでしょう。
業務中には連携がうまくいかない関係でも、イベントを通じて業務外のやりとりが生まれることで関係に変化が生じる可能性もあります。従業員同士のコミュニケーションが活性化されることで、会社への帰属意識も高まるでしょう。
2−2.従業員のモチベーション向上
イベントの実施は、従業員のモチベーションアップにも貢献します。運動会や社員旅行に消極的な場合でも、表彰式のような業務の功績を評価されるイベントは好まれる傾向があります。
周囲から実績を認められる達成感や、インセンティブや記念品による利益享受などによりモチベーションが高まると、さらなる成長効果も狙えるでしょう。従業員の成長は企業の成長につながるため、従業員と企業の両者にとってメリットの大きい福利厚生です。
2−3.企業文化の醸成
企業文化の醸成とは、企業が社員との間に独自の価値観やルールなどを形成することです。企業としての経営方針や実績を重ねていくことで積み上げられていき、企業の行動規範につながります。企業のイメージにも大きく影響するため、重要な観点です。
福利厚生で企業文化の醸成を目的とする場合、研修の実施が効果的といえます。研修を通じて企業文化を共有・浸透させることで、企業が一つにまとまっていくでしょう。
3.イベントの具体例とトレンド
実際に福利厚生を導入する場合、どのようなイベントを選ぶのが理想的なのでしょうか。イベントの具体例とトレンドは大きく分けて以下の3つです。
- 社内運動会やスポーツイベント
- 勉強会や研修イベント
- 社員旅行やアウトドア活動
それぞれの特徴を詳しく見てみましょう。
3−1.社内運動会やスポーツイベント
社内運動会や各スポーツイベントは、企業が実施する社内イベントの代表格といえます。コロナ以降は避けられる傾向がある福利厚生の一つですが、企業の伝統行事として愛されているケースも少なくありません。
運動会やスポーツを通じて一丸となって取り組むことで、チームワークの向上やコミュニケーションの活性化を期待できます。リフレッシュや運動不足の解消などもメリットといえます。ただし、運動会やイベントの実施には、事前準備や当日の運営など負担が大きい点は否めません。
3−2.勉強会や研修イベント
勉強会や研修イベントも、福利厚生としておすすめのイベントです。業務に関連する資格取得に向けた勉強会を開催したり、外部機関のセミナーに参加したり、交流を重視した研修イベントを設けたりと、従業員の向上心を高めるさまざまな形式のイベントを開くとよいでしょう。
必要なスキルや学習は、人によって異なります。従業員一人ひとりが今の自分に必要だと感じるセミナーに自由に参加できるようになると、向上心をより高められる可能性があります。定例のセミナーや研修を行うだけでなく、個別で柔軟に選べる機会を複数設けることで、仕事へのモチベーションアップにもつながるでしょう。
3−3.社員旅行やアウトドア活動
社員旅行やアウトドア活動は、コロナ以降ではやや選ばれにくくなった福利厚生といえます。コロナ禍で自粛した企業は、それ以来再開を控えたり、規模を抑えて開催したりと、以前よりも活動をセーブしている企業が少なくありません。
また、多様化が進む現代では、従業員の家族が同伴可能なイベントも好まれているとはいえない状況です。夫婦で休日が異なっていたり、プライベートを切り分ける考え方が浸透していたりと、働き方や時代の影響からも満足度の高いイベントにしにくい現状があります。
社員旅行やアウトドア活動にネガティブな印象を持つ従業員が多い場合は、日帰りにしたり自由時間を増やしたりと、ニーズにあわせた形での開催を検討したほうがよいでしょう。
4.福利厚生イベントを成功させるポイント
![]()
福利厚生イベントを成功させるには、どのような点を意識すればよいのでしょうか。ここでは、成功させるためのポイントを3つに分けてご紹介します。
- 目的を明確化する
- 参加しやすいスケジュール設定
- 従業員の意見を反映する
4−1.目的を明確化する
福利厚生に限らず、イベントを実施する際は明確な目的設定が重要です。社内イベントに関しては、従業員が楽しく過ごせるものにするだけでなく、そのイベントが企業にとってどのように還元されるかを考えておく必要があります。
社員旅行やアウトドア活動のようなレジャー要素の強いイベントであっても、必ず目的を明確にしておきましょう。福利厚生イベントの目的としてよく見られるものは以下のとおりです。
- 従業員のモチベーションの向上
- 従業員の満足度向上
- 従業員の離職率の低下
- チームビルディングによるパフォーマンスの向上
- コミュニケーションの活性化
- 優秀な人材の確保
- 社員の健康維持
- 採用力の向上
会社が抱える課題にあわせて目的を掲げ、イベントを企画していきましょう。
4−2.参加しやすいスケジュール設定
福利厚生は全員平等に利用できる制度にする必要があります。特定の社員しか参加できないスケジュールにすると、平等性に欠けたイベントになってしまうため、できる限り全員が参加しやすいスケジュールに設定しましょう。
全員参加が難しい場合は、カフェテリアプランのようにカスタマイズできる福利厚生にしておくと従業員が自分のスケジュールに合わせて利用できます。カフェテリアプランとは、企業が従業員にポイントなどを付与し、従業員がそのポイントを利用して自由に福利厚生メニューを選べる制度です。従業員のニーズにあったサービスを選べるため、効率的な福利厚生も実現できます。
4−3.従業員の意見を反映する
せっかく福利厚生に投資をしても、従業員にとって利用価値を感じられないものであれば効果は期待できません。従業員が本当に求めているイベントであるかどうかを確認するためにも、従業員からの意見を募ることが大切です。社内アンケートをとるなどして、従業員がどのようなイベントを望んでいるのかを確認しましょう。
従業員の要望は変化していくため、アンケートは一度でなく定期的に行うことも重要です。意見を都度反映させていくことで、よりニーズにあった福利制度に近づけるでしょう。また、イベントが終わったあとのアンケートも有効です。満足度の低いイベントは定例化せず、反省点を次のイベントに活かしていくなど、折々で従業員の意見を反映していきましょう。
5.イベント費用を福利厚生費にする条件
![]()
文化・体育・レクリエーション費用は原則、福利厚生費として計上できます。しかし、イベントにかかる費用がすべて福利厚生費に充当できるわけではありません。文化・体育・レクリエーション費用を福利厚生費として処理するためには、特定の条件を満たす必要があります。福利厚生費にするための条件は以下のとおりです。
- 全従業員が対象であること
- 常識の範囲内の金額設定
- 現金支給ではないこと
それぞれの条件について詳しく見てみましょう。
5−1.全従業員が対象であること
福利厚生費として扱うためには、全従業員を対象にした制度でなければ認められません。先述のように福利厚生は全員が平等に利用できるものでなければならないため、新入社員限定など対象者が限定されるイベントは課税対象になります。
5−2.常識の範囲内の金額設定
福利厚生費は常識の範囲内の金額でなければ認められません。例えば、従業員同士のコミュニケーションの活性化やモチベーションアップを目的とした懇親会を行う場合、一人あたりの食費が数万円かかるような設定では福利厚生費として判断されない可能性があります。
福利厚生費として計上される明確な基準はありませんが、あまりに高額だと課税対象になるおそれがあるためご注意ください。常識の範囲内の金額に留めておけば、基本的には問題ありません。
5−3.現金支給ではないこと
従業員に賞金などとして現金を支給した場合、金額を問わず課税対象になります。また、現物支給であっても数万円に及ぶような高額な物品の場合も課税対象としてみなされる可能性があることを覚えておきましょう。
あわせて読みたい
6.福利厚生イベントにおける注意点と対策
福利厚生イベントを実施する場合、従業員に喜んでもらえると思って取り入れたことが逆効果になるケースもあります。ここでは、注意点と対策について掘り下げましょう。
- 換金性の高い景品のリスク
- 従業員間の不公平感を防ぐ方法
- 法規制や税務リスクへの対応
6−1.換金性の高い景品のリスク
忘年会や新年会などの景品で、商品券を検討している方はご注意ください。商品券をはじめとする金券など、換金性の高い景品は現金と同様に扱われます。従業員に金券を渡した場合は課税対象となり、従業員の負担になることを覚えておきましょう。
忘年会や新年会で景品を出す場合は、物品にしておくことをおすすめします。物品であれば基本的に課税されません。しかし、物品であっても高額であれば常識の範囲を逸脱するため、高額でないものを選んでください。
6−2.従業員間の不公平感を防ぐ方法
福利厚生において平等性は不可欠であるため、従業員間の不公平感をどのように防ぐかは重要なポイントです。機会を平等に与えられる福利厚生としては、主に以下の3つが考えられます。
- 勤続年数に応じた記念品の贈呈
- 残業時の食事支給
- 自社商品の割引制度
福利厚生で報奨金を出す場合は、社内規程で明確な表彰基準を設けておき、勤続年数に応じた記念品を贈呈するなどしておくと非課税扱いになりやすいです。
また、残業した従業員への食事代支給も福利厚生費として認められますが、お酒が入ると交際費としてみなされる可能性があります。自社商品の割引制度、いわゆる社販制度はアパレル業界などで多く設けられており、企業・従業員の両者にとってメリットのある制度といえるでしょう。
6−3.法規制や税務リスクへの対応
福利厚生費は非課税として扱われるため、不正利用するケースも少なくありません。そのため、金券や高額な物品は税務署からも指摘を受けやすく、リスクが高いといえるでしょう。
また、少額であっても福利厚生は従業員全体に向けて用意するため、総額は高くなります。用途が不鮮明であると脱税行為を疑われるおそれもあるので、リスク管理のためにも用途は明記しておきましょう。
7.イベント開催に必要な5ステップ
実際にイベントを開催する場合、どのような工程で進めていけばよいのか迷う方も多いのではないでしょうか。イベント開催に必要なステップは以下の5つです。
- イベントを開催する目的を明確にする
- 企画案を作成する
- 従業員に告知して準備する
- イベントを開催する
- 振り返って改善点を次につなげる
7−1.イベントを開催する目的を明確にする
イベントの開催に向けて、改めて目的を明確にしましょう。先述したように、イベントも業務と同様に目的を持って開催することが大切です。企画段階で上がっていた目的を言語化させ、運営メンバーで共有してください。メンバー全員が一丸となり同じ目的意識でイベント実施に向けて動くことで、良質なイベントにつながります。
7−2.企画案を作成する
次に、設定した目的をもとに、企画案を作成します。目的が不鮮明なままだとこの段階から企画がずれていってしまい、不本意な仕上がりになる可能性があります。メンバー全員が目的を常に念頭に置き、意見を出し合っていきましょう。
イベントの形式や方向性が定まったら、詳細を決めていきます。プログラムの内容は、項目ごとに目的に沿ったものかを確認してください。そして、会社の年間スケジュールなどを参照し、全員が参加できる日時に設定することが大切です。詳細がまとまったら、告知用の書面を用意しましょう。
7−3.従業員に告知して準備する
従業員にイベントを告知する際には、すべての従業員が閲覧できる方法を採用してください。社内の掲示板やメール、社内SNSなどを利用して、従業員全体に告知しましょう。一定の社員だけに送らず、必ず全員に送られているかどうかを確認してください。
イベントの告知と平行して、開催の準備も進めていきます。自社開催の場合は使用する会議室などをおさえておき、外部会場の場合は早めに予約しておきましょう。イベントで使用する機材のレンタルが必要であれば、その手配も行います。食事や景品の支給があれば、それぞれ運営メンバーから担当を割り振り、効率的に準備をするとよいでしょう。
当日はスムーズに進行できるよう、運営マニュアルを用意しておくことが大切です。屋外を利用する場合は、雨天時のプログラムも検討しておく必要があります。運営メンバーの病欠や参加者のけが・急病などイレギュラーな事態も想定しておき、あらゆる場面で迅速に対応できるようにしておきましょう。
7−4.イベントを開催する
イベントの準備が整い、当日を迎えたらいよいよ開催です。運営マニュアルの大枠を頭に入れておいた状態で本番を迎えると、スムーズに進行しやすくなります。詳細は適宜確認して、ミスや漏れのない対応に努めましょう。
イベントでは参加者が多ければ多いほどイレギュラーな事態が起こりやすくなります。運営メンバーの役割や配置に問題がないか確認しておき、効率的な運営を目指してください。また、運営メンバーだけでは人手が足りない場合は、事前に協力者を募りメンバーを増員しておいたほうがよいでしょう。
7−5.振り返って改善点を次につなげる
イベントの終了後は、必ず振り返りを行いましょう。イベントが完了してそのままだと、効果を十分に活かせなくなる可能性があります。運営メンバー内で振り返りを行い、当初の目的に沿っていたかどうかを確認してください。そして、メンバーそれぞれの感想や意見を寄せ合い、次のイベントに向けて反省点や改善点をまとめましょう。
運営メンバーだけでは客観的な判断が難しいため、参加者からのアンケートも不可欠です。無記名にするなどの配慮も柔軟に取り入れると、率直な意見が集まりやすくなります。意見がそろったら報告書にまとめましょう。
8.イベント参加率向上のための工夫
社内イベントは一定の従業員から避けられる傾向があることは否めません。福利厚生をより多くの従業員に利用してもらうためにも、イベント参加者を増やせる工夫を盛り込みましょう。ポイントは以下の2つです。
- 事前のアンケートを活用する
- 参加の義務化を避ける
8−1.事前のアンケートを活用する
社内イベントの立案時には、企画を本格的に進める前にアンケートを行うことをおすすめします。運営メンバーにとっては魅力を感じる内容でも、社内全体ではニーズが低い可能性も考えられます。企画を進めてからニーズが低いことがわかると無駄が増えてしまうため、早めの段階で興味があるかどうかを確認しましょう。
目的を達成するためにも、一人でも多くの従業員が参加することが大切です。少数の参加では目的を果たしにくくなり、福利厚生としてうまく機能しなくなります。事前アンケートの結果にネガティブな意見が多い場合は、その意見を反映させて従業員が参加したいと思える企画に練り直しましょう。
8−2.参加の義務化を避ける
福利厚生のイベントでは全員の参加が望ましいですが、強制参加にするのは控えましょう。また、不参加の場合、評価に影響を与えるのもNGです。従業員が義務的に参加している状態では、目的を達成するどころか遠ざかりかねません。
強制参加のイベントでモチベーションの向上は期待できません。帰属意識にもつながらず、悪循環を招くだけになるので、従業員が参加したくなる工夫を重視しましょう。
9.まとめ
福利厚生のイベントでは、一人でも多くの従業員が自発的に参加したくなるような工夫が欠かせません。アンケートを積極的に導入し、従業員のリアルな声を柔軟に取り入れてニーズにあったイベントを実施しましょう。
また、近年の福利厚生では、多様化するニーズに幅広く対応できるカフェテリアプランの導入が増えています。社内表彰のようなモチベーションにかかわるイベントだけでなく、従業員一人ひとりが快適に利用できる選択制の福利厚生が支持される時代といえるでしょう。
福利厚生にお悩みの方は、ぜひイーウェルにお任せください。イーウェルでは、企業のニーズに合わせた福利厚生サービスを提供し、従業員の満足度向上を叶えます。
イベントの実施にお悩みの方、現代にフィットした福利厚生にご興味のある方は、ぜひ一度ご相談ください。
社内コミュニケーションを活発にし、従業員の働く意欲を高める「インセンティブ・プラス」
ポイントを使って評価や感謝を伝え合うことで社内コミュニケーションを活性化するWEBサービスです。
関連キーワード
Related keywords
関連記事
Related article
おすすめ記事
Recommend