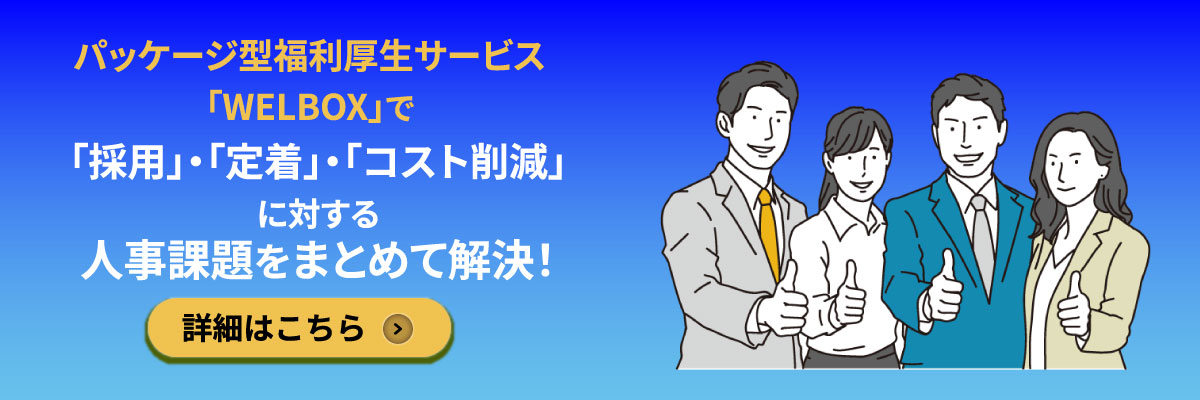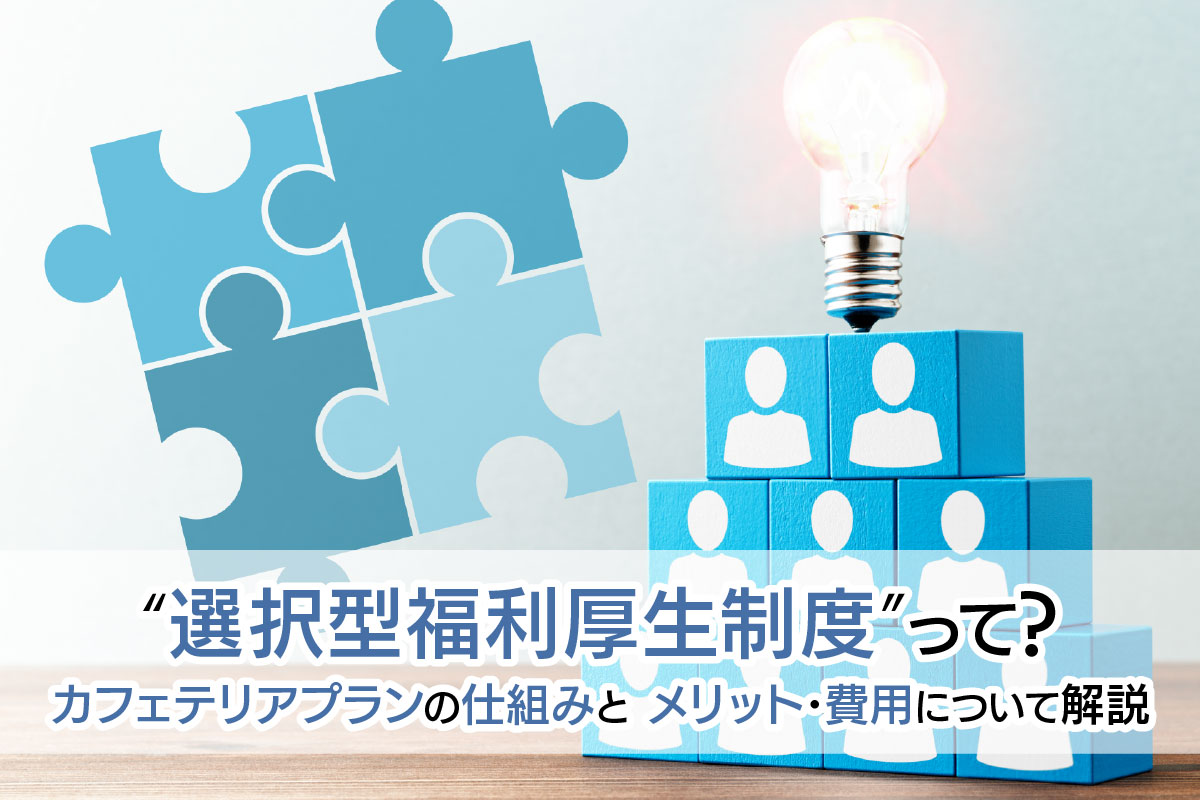福利厚生が離職率に与える効果とは?人材定着を実現する方法と成功事例

「離職率の高さが企業経営の課題となっており、効果的な対策を検討している」
「福利厚生制度の見直しを通じて、従業員の定着率を向上させたい」
福利厚生制度の適切な設計と運用は、離職率の大幅な改善と企業の競争力向上を同時に実現する重要な経営戦略です。日本企業の平均離職率は約15%で推移していますが、福利厚生を充実させた企業では高い離職率を大幅に改善したケースもあります。
本記事では、離職率の現状分析から従業員が離職を考える理由、離職防止に効果的な福利厚生施策の設計方法まで、人事担当者が知っておくべき実践的な情報を詳しく解説します。
目次
1.離職率の現状

日本企業は深刻な人材流出問題に直面しており、毎年約6~7人に1人が離職している現状があります。特に若手人材の早期離職と業種間格差が大きな課題となっています。
厚生労働省の「雇用動向調査」によれば、日本企業の離職率は近年15%前後で推移しており、2024年は14.2%でした。
特に注目すべきは新卒者の早期離職率です。2020年春卒業の大学生のうち約32.3%が3年以内に離職しており、企業にとって採用コストや研修投資の回収が困難な状況が続いています。
業種別では宿泊業・飲食サービス業が18.1%と突出して高く、建設業9.7%、製造業8.8%と業種による大きな格差があります。
2.従業員が離職を考える主な理由
従業員の離職要因は主に「給与・労働条件・人間関係」の3つの職場環境要因に集約される傾向があります。
給与・評価に対する不満が最も大きな離職要因です。
努力や成果に見合った評価を受けられない、適正な給与水準ではないと感じることで、従業員のモチベーションは大幅に低下します。同業他社との待遇格差を認識した場合や、昇進・昇格のタイミングで不公平感を抱いた際には、特に離職意向が強まる傾向があります。
長時間労働や休暇が取得しづらい労働環境も重要な離職要因でしょう。
慢性的な人員不足により残業や休日出勤が常態化し、有給休暇の取得が困難な環境では、従業員の心身への負担が蓄積されます。また管理職は、部下のサポートや業務調整により自身の休暇取得が後回しになりがちで、燃え尽き症候群のリスクが高まる状況下にあります。
職場の人間関係悪化とハラスメント問題は、職場環境を根本的に悪化させる要因です。上司や同僚とのコミュニケーション不全、パワハラ・セクハラの横行する職場では、直接の被害者以外も職場全体の雰囲気悪化を感じ、退職者が増加する悪循環に陥ってしまいます。
3.離職率が高い企業の特徴
離職率が高い企業には、以下のような共通した特徴が見られます。
- 正当な賃金や評価が受けられない
- 長時間労働
- 休みが取りづらい
- 働き方の選択肢が少ない
- ハラスメントの横行など人間関係が悪い
- 福利厚生が乏しい
3-1 正当な賃金や評価が受けられない
評価制度が不十分な企業では、従業員の努力や成果が適切に報酬に反映されづらい傾向にあります。評価基準の曖昧さ、上司の主観に左右される人事考課などは、従業員に将来への不安を抱かせる要因となります。
3-2 長時間労働
サービス残業や過重労働が放置されている企業では、従業員の心身の健康が損なわれ、結果として離職率が高まります。管理職の労働時間管理が不十分な企業ほど、現場負担が増大する傾向にあります。
3-3 休みが取りづらい
有給休暇取得への理解不足や、人員不足による代替要員確保の困難により、従業員が休暇を取得しにくい環境は離職促進要因となります。
3-4 働き方の選択肢が少ない
リモートワークやフレックスタイムなどの制度がなく、画一的な働き方しか認められない企業では、ライフステージの変化に対応できず離職につながりやすくなるでしょう。
3-5 ハラスメントの横行など人間関係が悪い
パワハラ・セクハラに対し適切な対応がなされない職場では、被害者だけでなく周囲の従業員も職場環境に不安を感じ、離職率が上昇します。
ハラスメントに該当しないまでも、コミュニケーション不全に陥っている職場では、必要な情報が届かなかったり、モチベーションアップがしにくかったりすることもあります。
会社に伝えなかった本当の退職理由の第1位は「人間関係が悪い」だったとする調査結果もあるくらいです。
3-6 福利厚生が乏しい
法定外福利厚生の整備が不十分で、従業員の生活をサポートする制度が少ない企業では、他社との比較により魅力度が低下し、人材流出が起こりやすくなります。
法定外福利厚生は、社外からでも確認できる「会社がこれだけ従業員を大切にしています」というメッセージです。最近の求職者は、会社を選ぶ際にも福利厚生の充実度を気にする傾向が強くなっています。
4.従業員の離職を低減させるためには?

効果的な離職防止施策は以下の3つの領域に分けられます。
- 待遇や福利厚生の見直し
- 企業理念や経営計画を共有する
- 配属のミスマッチを防ぎキャリア形成をサポートする
4-1 待遇や福利厚生の見直し
賃金水準の適正化と福利厚生の充実は、離職率低下に最も直接的で効果的な施策の一つといえるでしょう。市場価値に見合った給与水準の設定、透明性の高い評価制度の構築、成果に応じた適切な昇給・昇進制度の整備が求められます。
具体的には、同業他社との給与水準比較調査の実施、評価基準の明文化と従業員への周知、定期的な人事考課面談の実施などが効果的です。また、福利厚生制度についても従業員のニーズを把握し、実際に利用価値の高い制度を優先的に導入することが重要です。
4-2 企業理念や経営計画を共有する
経営陣のビジョンが従業員に適切に伝わらないことが、将来不安による離職の大きな要因となることがあります。定期的な全社集会での経営方針説明や、経営陣と現場社員との対話機会を意識的に作ることが実は効果的です。
従業員が自分の業務が会社の成長にどのように貢献しているかを理解できれば、仕事に対するやりがいや帰属意識が向上します。また、将来のキャリアパスを明示することで、従業員の不安を解消し、長期的な視点で会社に貢献する意欲を高めることができます。
4-3 配属のミスマッチを防ぎキャリア形成をサポートする
採用段階での相互理解を深め、入社後は定期的な面談やキャリア相談の場を設けることで、従業員が自分のキャリアプランを描けるよう継続的にサポートすることも必要です。
入社3年以内の離職率が高い現状を踏まえ、新入社員へのメンター制度の導入や、定期的なキャリア面談の実施により、早期のミスマッチ発見と対策を行うことも重要です。
5.従業員の離職を減らすことで企業が得られるメリット
離職率の低下により、企業は採用・育成コスト削減と生産性向上を通じて収益性を大幅に改善できます。
最も直接的なメリットは採用・育成コストの削減効果です。
人材採用には求人広告費、エージェント手数料、面接対応コスト、入社後の研修費用など多大な費用が必要になります。一般的に1名採用に必要なコストは年収の3〜6ヶ月分とされており、定着率向上によりこれらコストの節約が可能となるでしょう。
人材定着による業績向上も重要な効果といえます。
従業員の在籍期間延長により業務熟練度と生産性が向上し、企業全体のパフォーマンス向上につながります。顧客との継続的な関係構築が可能となり、サービス品質向上と顧客満足度向上も期待できるでしょう。
また、低離職率企業は「働きやすい会社」として社外から高評価を得ることもできるため、優秀な人材確保が容易になります。これにより採用市場での競争力向上を実現し、より良い人材獲得という好循環を生み出すことができるでしょう。
6.従業員の離職率を下げるための効果的な福利厚生

離職率の低下に効果的な福利厚生制度は、従業員の多様なニーズに対応する4つの主要分野に分類できます。
- 健康・ヘルスケア関連
- 自己啓発・スキルアップ支援
- ワークライフバランス支援
- 資産形成支援
6-1 健康・ヘルスケア関連
健康支援制度は離職防止における基本的かつ効果的な福利厚生です。健康は全活動の基盤であり、従業員の健康維持は企業の生産性向上に直結します。
具体的な施策として、定期健康診断の充実、人間ドックの費用補助、予防接種の会社負担、社内での健康相談窓口の設置などが挙げられます。また、近年では心理的な健康面でのサポートも重要視されており、社外EAP(従業員支援プログラム)への相談体制整備やストレスチェックの実施も効果的な取り組みとなっています。
社内フィットネス施設の設置やスポーツクラブの法人契約、健康増進セミナー開催なども、従業員の健康意識向上と職場満足度向上に寄与します。
6-2 自己啓発・スキルアップ支援
スキルアップ支援制度は「この会社で成長できる」という実感を提供し、将来への不安を解消します。従業員がスキルアップすることで、新しい視点を取り入れて業務効率化できる場合もありますし、生産性向上にもつながっていくでしょう。
書籍購入補助、通信教育や資格取得費用補助、外部セミナー・研修参加費用負担、語学学習支援などが効果的です。近年注目されているリスキリング(学び直し)支援も重要な取り組みで、変化の激しいビジネス環境に対応できる人材育成につながります。
また、社内勉強会の開催支援や、業務時間内での学習時間の確保なども、従業員の成長意欲を支援する効果的な制度です。
6-3 ワークライフバランス支援
ワークライフバランス支援制度は離職防止に直接的で即効性の高い効果をもたらします。
具体的な施策として、リフレッシュ休暇、アニバーサリー休暇、家族の記念日休暇等の特別休暇制度などがあります。また最近では、在宅勤務制度やフレックスタイム制度、時短勤務制度の導入により、従業員が自分のライフステージに合わせた働き方を選択できる環境を提供することも重要になってきています。
育児・介護と仕事の両立支援として、保育所の設置・提携、介護相談窓口設置、育児・介護休業取得促進などの施策を法定以上に拡充することも近年求められるようになっています。
6-4 資産形成支援
資産形成支援制度は将来不安を解消し、「この会社にいれば安心だ」という安心感を醸成します。老後資金への不安が高まる現代において、企業による従業員の資産形成サポートは大きな魅力となるでしょう。
財形貯蓄制度、企業型確定拠出年金、従業員持株会などの制度により、従業員の計画的な資産形成をサポートできます。金融リテラシー向上のためのセミナー開催や資産運用相談窓口設置も効果的でしょう。
住宅関連では、住宅購入資金の低金利融資や住宅手当の支給、社宅・寮の提供なども、従業員の生活基盤安定に大きく貢献します。
6-5 従業員の要望に沿った福利厚生を取り入れることも大切
福利厚生制度の成功の鍵は、従業員の実際のニーズに合致した内容であることです。定期的な従業員アンケートの実施により満足度やニーズを把握し、制度を利用しやすい環境を整えることも必要になってきます。
世代や職種、家族の有無などさまざまなバックボーンにより、求められる福利厚生は異なるため、多様な選択肢を用意することが効果的です。例えば、若手従業員は自己啓発支援を重視し、中堅層は家族関連の支援を、ベテラン層は健康関連や資産形成支援を重視する傾向があります。
7.離職率改善に成功した企業の具体例
福利厚生施設だけでなく、福利厚生全般に関して、新しい制度を導入する際には、それが本当に従業員に利用され、価値を還元できるものなのか、現在導入している福利厚生との整合性は取れているかなど、広い視点で検討することが重要です。
7-1 サイボウズ株式会社
ソフトウェア開発のサイボウズは、2005年に離職率28%という危機的状況から、現在4%まで劇的な改善を実現しました。同社の成功の鍵は「100人いれば100通りの働き方を追求する」という大胆な人事制度改革にありました。
同社が導入した「働き方宣言」制度では、従業員一人ひとりが勤務時間や勤務地を自由に選択できます。また、子連れ出勤制度、退職しても6年以内なら復帰できる「育自分休暇制度」など、従来の常識を覆すユニークな制度を導入しています。
これらの制度により、従業員は自分のライフステージに合わせた働き方を選択でき、結果として離職率の大幅な改善を実現しました。
参考:サイボウズは「100人100通りの働き方」をやめます。社員数1000人を超えても、成長と幸福を両立させるための挑戦(サイボウズ式)
7-2 株式会社鳥貴族
外食産業の鳥貴族は、創業当初から「働きやすい職場作り」に力を入れ、業界の常識を覆す制度改革で離職率改善を実現しました。離職率の高い外食業界において、同社は業界平均を大幅に下回る離職率を維持しています。
同社では時間外労働の規制強化、休日出勤の原則禁止、サービス残業の一切禁止といった厳格な労務管理を徹底しています。また、現場主体での働きやすい環境づくりを推進し、店長の労働時間管理にも細心の注意を払っています。
7-3 ユーソナー株式会社
ユーソナー株式会社は「みんなが親孝行できる会社」をビジョンに掲げ、従業員に「時間・お金・心」の3つの余裕を与える独自の福利厚生で注目を集めています。
同社では長期の夏季休暇取得推奨、無料のランチ支給、社外カウンセラーへの相談体制、社内サラダバーの設置など、従業員の心身の健康と生活の充実を支援する包括的な制度を導入しています。これらの制度により従業員満足度を大幅に向上させ、高い定着率を実現しています。
7-4 株式会社クレイジー
ウエディング事業の株式会社クレイジーは、年間の休暇日数に上限を設けない「グレートジャーニー制度」を導入しました。この制度では、従業員が必要に応じて長期休暇を取得でき、海外旅行や家族との時間など、個人の価値観に合わせた休暇の使い方が可能です。
社長自らこの制度を積極的に活用し、部下にも遠慮なく休暇を取るよう奨励することで、「お互い様」の企業文化を醸成しました。結果として、従業員の仕事に対する集中力とモチベーションが向上し、生産性の大幅な改善を実現しています。
8.福利厚生の種類を選ぶ際に注意しておくポイント
離職率改善を見据えた福利厚生制度の成功は「利用しやすさ」と「継続的な見直し」にかかっています。以下のポイントを押さえることが重要でしょう。
- 利用しやすい制度設計
- 定期的なニーズ把握
- コストと効果のバランス
- 制度の偏り防止
申請手続きのハードルを下げ、従業員が躊躇なく制度を利用できる環境づくりもが重要です。複雑な申請手続きや上司の承認が必要な制度では実際の利用率が低下しがちだからです。デジタル化による申請簡素化や自動承認システム導入も効果的な取り組みです。
従業員ニーズは時代とともに変化するため、定期的に制度を見直すべきか検討する機会を設け、従業員にアンケートなどで意見を聞くことが必要です。世代交代や事業環境変化により求められる福利厚生内容も変化するため、継続的な調査が重要でしょう。
限られた予算で最大効果を得るには、全従業員が恩恵を受けやすい制度への優先投資が求められます。一部従業員のみが利用する高額制度よりも、多くの従業員が日常的に活用できる制度の方が全体満足度向上につながるでしょう。
利用率データの定期分析により、特定世代や職種に偏らないバランスの取れた制度設計を心がけることも重要です。多様な従業員ニーズに対応できる包括的な制度体系の構築が求められます。
なお、同業他社と横並びの福利厚生では、離職率低下、採用力強化の決め手にはならないとも言われます。上記に挙げた4つのポイントを押さえた福利厚生を最低限として、従業員の心をつかむユニークな制度を構築したり、与えられたポイントを自分の必要なものに自由に使える「選択型福利厚生カフェテリアプラン」を導入したりするなど、工夫して魅力アップを図っていくべきでしょう。
あわせて読みたい
9.まとめ
福利厚生制度の適切な設計と運用は、離職率の大幅改善と企業競争力向上を同時に実現する重要な経営戦略です。
従業員の離職理由を正確に把握し、健康・ヘルスケア、自己啓発・スキルアップ、ワークライフバランス、資産形成支援といった多角的なアプローチから効果的な福利厚生制度を構築することで、大幅な改善が可能です。
成功企業事例からも明らかなように、従業員一人ひとりを大切にする企業文化の醸成と、従業員のニーズに合致した制度設計が成功の鍵となります。人材こそが企業の最も重要な資産である現代において、福利厚生制度を通じた離職率改善は、持続的な成長と競争優位性確保のための必須の取り組みといえるでしょう。
離職率改善を目的とした総合的な福利厚生制度の構築をご検討の場合は、福利厚生のトータルソリューションを提供するイーウェルにご相談ください。パッケージ型福利厚生サービス「WELBOX」により、人材定着と離職率改善を実現する包括的なソリューションをご提案いたします。
介護・育児・自己啓発・健康増進・旅行やエンターテイメントなど、多彩なメニューがパッケージとなっている福利厚生サービスです。充実した福利厚生を目指すなら「WELBOX」
従業員のライフスタイル・ライフステージに応じて、メニューを選択しご利用いただくことが可能です。
関連記事
Related article
おすすめ記事
Recommend