アメリカのエンゲージメントとは

人事領域におけるエンゲージメントという概念は1990年代にアメリカで生まれました。「従業員エンゲージメントとは、会社と従業員との間の信頼関係が構築され、従業員が会社に対して貢献したいと思い、相互での愛着心があること」と、アメリカの心理学者ウィリアム・カーンが提唱したと言われています。
目次
1.アメリカでのエンゲージメントの考え方とは

1990年代のアメリカ企業では生産性向上の意識が高まり、従業員エンゲージメントという考え方が注目されるようになっていきました。それまで大多数の企業は従業員満足度に重きを置いていましたが、従業員が求める給与・福利厚生などを与えるだけでは、生産性向上にはつながりにくいことに気付いたのです。そこで注目されたのが、エンゲージメントの考え方ということになります。
アメリカ企業は、個人主義が強く、従業員の解雇も容易なことから、優秀な人材を企業に残す方法として、エンゲージメントが広く普及していったと考えられます。
2. アメリカのエンゲージメントが注目される理由
アメリカでは、国をあげてHRテックへ投資していることや、大企業が率先してエンゲージメントを大切にした働き方やオフィスづくりに取り組んでいるため、国民1人1人の意識も日本とは大きく異なっているようです。以下の記事ではアメリカのエンゲージメントが注目される理由について3点ご紹介していきます。 
理由①HRテック先進国のため
アメリカはHRテック先進国といわれています。アメリカやヨーロッパなど海外では、企業がHRテックを利用し、社員1人当たりに日本円で年間約2万2,000円の投資をしています。特にアメリカでは多くの企業が人的資源投資の視点から社員のエンゲージメント向上を目的にHRテックを利用しています。
引用元:HR NOTE『業界の最先端を行く海外HR Tech』
https://hrnote.jp/contents/hitoteku-grobal-20191211/
アメリカ企業は、HRテックへの投資額がとても大きいことで知られています。アメリカのHR業界のデータを調べてみると、2012年~2016年の間アメリカが世界市場の62%を占め、シェアはNo.1となっています(2018年の日本のHRテック市場規模は、2.7%)。
その市場規模は、2016年:1兆5,000億円、2018年:2兆3,000億円となっており、毎年マーケットが拡大を続けていることがわかります。しかし、日本のHRマーケットを見てみると2019年で355億円ほどにとどまっているのです。
引用元:株式会社アックスコンサルティング『HR BLOG』
https://motifyhr.jp/blog/engagement/interview_hirose/
引用元:カオナビ人事用語集『HRテックの海外トレンドと今後の展望』
https://www.kaonavi.jp/dictionary/hrtech_trend/
海外でも注目のアメリカのHRテック企業例として、2019年に開催されたHR TechXpo 2019(※1)でファイナリストに残った企業を紹介します。
・企業名:MOODBIT https://mymoodbit.com/index.html
・サービス名:MOODBIT
『チームの“雰囲気”を見える化し、全ての組織を「ドリームチーム」へ』
Moodbit(ムードビット)は、社員がモチベーションや抱える課題に関する定期的な質問に答えることで、社員のリアルタイムな感情を確認できるツールです。質問の回答結果を分析し、結果に応じたアクションプランを立てることで、社員が常に満足度の高い状態で働くことができます。離職率の軽減やエンゲージメントの向上につながることが評価されています。
引用元:HR NOTE『業界の最先端を行く海外HR Tech』
https://hrnote.jp/contents/hitoteku-grobal-20191211/
※1 サンフランシスコで開催されているカンファレンスで、サンフランシスコのHRとHR Tech企業を結びつけるイベント
理由②世界的企業の取り組み
アメリカのGoogleやAdobeといった世界的企業では、実際にエンゲージメントを大切にした働き方やオフィスづくりに取り組んでいます。欧米においては、企業の業績を左右するものとしてエンゲージメントの概念が定着しているのです。
理由③ひとりひとりの意識の違い
日本では世間一般的に働き方改革のことを仕事と生活を分けて考える「ワークライフバランス」と言われていますが、アメリカではワークライフバランスというよりも「ワークライフインテグレーション」や「ワークライフフィット」と言われ、仕事と生活の統合を意味していることが多いようです。
仕事とプライベートを分けるのではなく、睡眠を除いたすべてが仕事であり趣味であるという考え方になります。この考え方だと「仕事が楽しいから、夜遅くまで会社にいたい人はいればいい」となりますが、日本人の一般的な考えだと「なるべく遅い時間まで残業はせずに帰宅する必要がある」となります。
このようなひとりひとりの仕事への意識もアメリカが注目されている理由の1つになっていると考えられます。
3.日本でエンゲージメントの考え方が注目される理由
企業と従業員、企業と顧客の関係性を表す指標としての「エンゲージメント」という言葉を日本でも多く耳にするようになってきました。その要因として近年は働き方改革が大きく叫ばれ、それに加え新型コロナウィルスの影響により職場環境や働き方、さらに会社のあり方そのものが加速しながら変化し、以前の形に戻ることはないと考えられています。
このような変化の中で社員の定着や活躍、生産性向上がさらに重要視され、「エンゲージメント」という言葉が注目を浴びるようになってきました。その背景には下記のようなことがあげられます。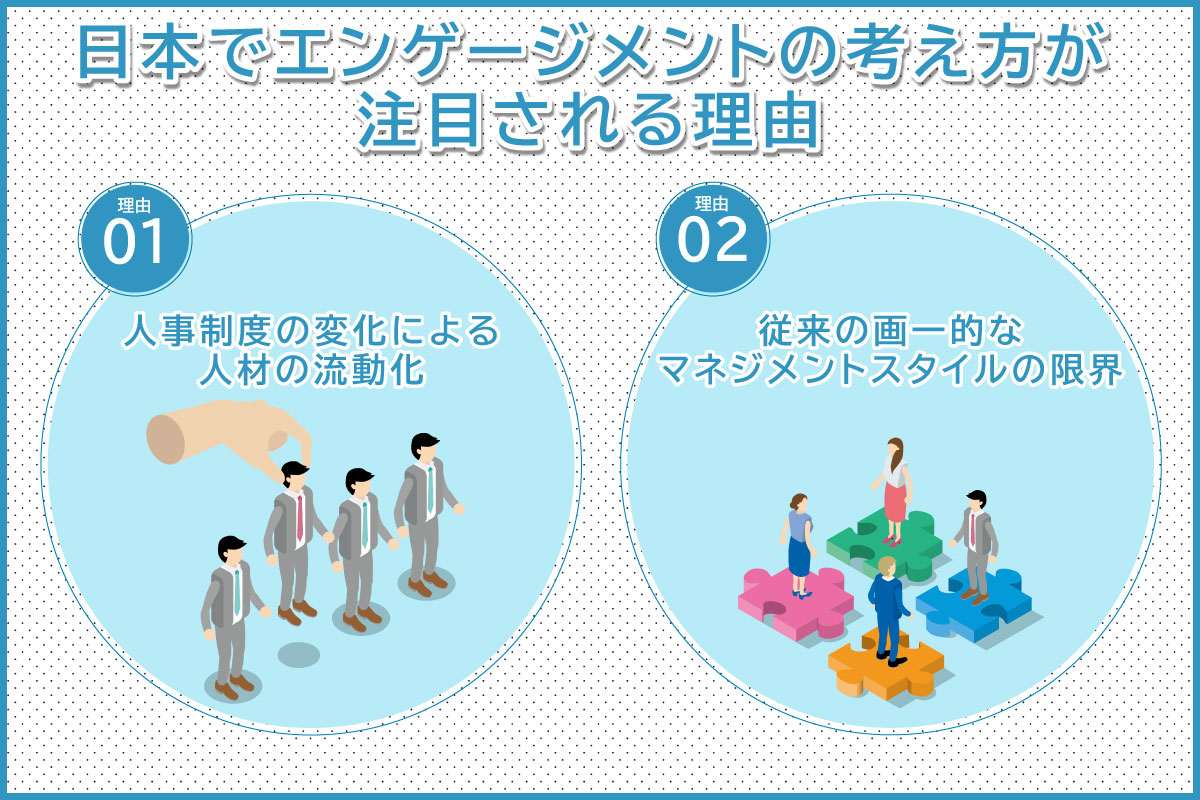
理由①人事制度の変化による人材の流動化
かつて日本の人事制度は「終身雇用」や「年功序列」が主体でしたが、近年では「成果主義」を導入する企業が増加しました。働き手はより良い環境や条件を求めて転職をするようになり、人材の流動化が進んでいるのです。
このような背景から、企業はいかに優秀な人材を採用するか、そしてどのようにして人材を社内に留めておくかを考える人事施策が重要となってきたのです。
理由②個人の価値観の多様化による従来のマネジメントスタイルの限界
雇用形態や個人の価値観が多様化し、働くモチベーションについても多様な価値観が存在するようになりました。給与額を重視することや出世をすることより、やりがいを重視する人や、会社の文化や雰囲気、業務内容などが自分に合わないと感じたらすぐに会社を辞めるという選択する人も珍しくありません。
そのため、従来の画一的なマネジメントスタイルでは、多様化した個人のモチベーションを保つことが難しくなってきています。多様な価値観を持つ個人がやりがいをもって働き続けられる職場環境づくりが求められているのです。
個々人の会社に対するエンゲージメントが低い状態だと、不満が組織にまん延し、社内全体の生産性が下がり、さらには離職しやすい状況に陥ってしまいます。そのためエンゲージメントの高い企業を構築することができれば、人材が定着し、長期的な企業の業績・生産性の向上につながっていくのです。
4.まとめ

2000年以降アメリカなどの欧米企業で定着したエンゲージメントという概念は日本にも広がりはじめ、外資系企業などで取り入れられるようになりましたが、終身雇用や年功序列の人事制度が主体だった当時の日本では、エンゲージメントの高さや低さにかかわらず1社に勤め続けることが良しとされてきました。
しかし時代は変化しています。現在の日本では「健康経営」「働き方改革」「組織力強化」「離職抑制」といった様々な観点からエンゲージメントが注目されるようになってきました。個人の価値観や個人と組織の関係性が変化を続けているこの時代だからこそ、今後さらにエンゲージメントは重要性を高めていくと考えられます。
エンゲージメントの向上は、企業競争力強化に直結します。ぜひエンゲージメントの必要性を理解いただき、アメリカ企業を参考により良い企業づくりに活かすことが望まれています。
関連キーワード
Related keywords
関連記事
Related article
おすすめ記事
Recommend
















