福利厚生はいらない?現代の福利厚生事情と効果的な見直し方法を解説
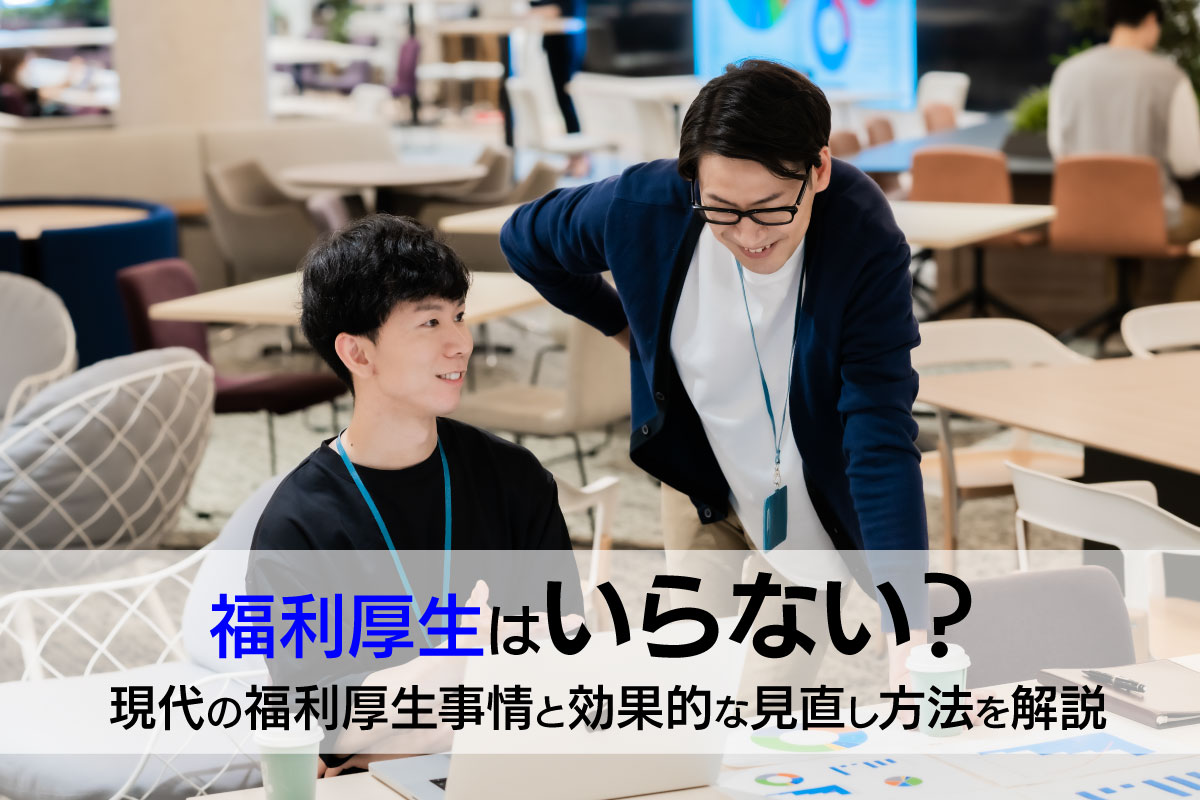
「せっかく導入した福利厚生制度なのに、従業員からの反応がイマイチ…」
「予算をかけて福利厚生制度を充実させているが、利用者が年々減っている」
そんな悩みを抱えている人事担当者は少なくありません。
近年、従業員からの「福利厚生はいらない」「賃金で還元してほしい」という声も増えており、特に従来型の福利厚生制度は「時代遅れ」「使いにくい」という指摘も多く聞かれます。
本記事では、福利厚生が「いらない」と言われる理由から、効果的な制度の見直し方法まで、人事戦略に役立つ実践的な情報をお伝えします。

目次
1.福利厚生が「いらない」と言われる理由

従業員から福利厚生制度への不満が高まっている主な理由は以下の3つです。
- 利用率が低い
- コスト増加
- ニーズの変化
- 賃上げの必要性と期待
1-1 利用率が低い
福利厚生制度の最大の課題は、制度があっても実際に利用されないことです。
手続きが煩雑で時間がかかると、従業員は利用する意欲を失ってしまいます。たとえば、申請書類が多数必要だったり、承認までに何週間もかかったりする制度では、せっかくの福利厚生も活用されません。
テレワークが普及した近年では「オフィスに行かなければ利用できない」制度は敬遠され、形骸化するケースが増えています。オフィス内の売店や社員食堂といった施設型の福利厚生は、リモートワーク中心の働き方では利用機会が大幅に減少してしまいます。
多くの企業で導入されている各種制度でも同様の傾向が見られます。企業独自の福利厚生制度の多くで利用率の低下が報告されており、制度の複雑さや実用性の低さが主な原因として挙げられています。特に手続きが煩雑な制度ほど敬遠される傾向が強くなっているのです。
1-2 コスト増加
利用されない制度にかかる企業負担は無駄な支出となり、他の重要な投資に充てる資金を減らしてしまいます。
福利厚生制度の導入には初期費用だけでなく、運営・管理費用も継続的に発生します。制度の説明資料作成、従業員への周知活動、利用手続きの管理など、人事部門の工数も相当なものになるでしょう。
特に中小企業にとって、利用されない制度のためにコストをかける余裕はなく、常に費用対効果を見直す姿勢が求められているのです。
1-3 ニーズの変化
働き方やライフスタイルの多様化により、従業員が求める福利厚生も変化しています。
リモートワークの普及で通勤手当の必要性が低下する一方、自宅での仕事環境整備への補助が求められるようになりました。
多くの福利厚生制度が「時代遅れ」と言われる背景には、個人向けの民間サービスや制度が充実してきたことが挙げられるでしょう。例えば資産形成分野では、つみたてNISAやiDeCoなどの税制優遇制度が整備され、個人の裁量で運用方針を決められる自由度の高さが魅力となっています。また、レジャーや健康管理についても、個人向けの多様なサービスが低コストで利用できるようになり、「会社の制度を使うより個人で手配した方が良い」という声が増えています。会社が保養所を所有していても、「毎年同じ場所しか行けない」ために敬遠されるケースもありますし、保養所に宿泊する際の価格の安さより、施設の設備やサービスの質、得られる体験の多様さなどに重きを置く傾向も見られます。
広く世の中で多様性が認められるようになり、従業員がある程度の種類の中から、自分の使いたいものを幅広く選べるようにしてほしいという、福利厚生に求められるニーズが変化してきた結果といえます。
1-4 賃上げの必要性と期待
近年の物価高の影響、また世の中的な流れから言っても、賃上げムードが高まっています。
最低賃金の全国平均は2003年度以降毎年引き上げられていますが、2023年には前年より43円、2024年は51円の引き上げとなり、2025年には過去最大の63円アップとなっています。
それに伴い、労働組合等の賃上げ交渉も毎年活発になっており、春先の春闘での結果に注目している方も多いのではないでしょうか。
福利厚生については、「福利厚生を拡充する分を、すべて賃金で従業員に還元した方がいいのではないか」という根強い議論もあります。
会社の資金は限られているため、使われない場合もある福利厚生にかけるよりは、個々の従業員の手元に賃金として配ってほしいと思う方も多いでしょう。
しかし、福利厚生にはさまざまな側面があり、一概に全部を賃金換算にしてしまってよいものでもありません。賃上げか福利厚生か、という二者択一でだけ考えるのには少々問題があります。
例えば若手社員などは、基本の給料が少ない分を家賃補助やさまざまな手当・優遇措置などで補っているケースもあります。福利厚生分を賃金換算にする場合には、基礎給与が多い役職者やベテラン社員にその分多く分配されかねませんが、福利厚生制度は基本的に平等な制度であり、一定の縛りはあるものの、基本給の多寡によって変わる制度はあまりありません。
賃上げムードに乗って福利厚生を削ってしまう前に、一度会社全体として制度を考える必要があるでしょう。
2.法定福利厚生は必須
福利厚生の見直しを検討する際には、法定福利厚生と法定外福利厚生の違いを理解して検討することが必要です。
法律で義務付けられた法定福利厚生(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険など)は、企業が必ず提供しなければならない制度です。これらは従業員の基本的な生活保障を担う重要な仕組みであり、企業規模や業種を問わず適用されます。
法定福利厚生費は企業の人件費の約15%を占めており、決して軽視できない負担ですが、法的義務である以上削減することはできません。
一般に求人などの場面で「福利厚生なし」とされている場合は、法定外福利厚生がないという意味であり、その場合でも法定福利厚生は備えられていることを理解しておきましょう。
したがって、企業が検討すべきは法定外福利厚生の内容や運用方法ということになります。
ここに企業の創意工夫の余地があり、従業員満足度向上と経営効率化の両立を図ることができます。
3.従業員から「いらない」と思われている福利厚生

多くの企業で従業員から敬遠されがちで、利用率が低くなる傾向にある福利厚生として、以下のようなものが挙げられます。
利用率が低い傾向にある福利厚生
- 社員旅行・レクリエーション
- レジャー施設の優待券
- オフィスコンビニ
- 託児所・育児支援
- 出産お祝い金・育休手当
社員旅行が最も不人気な理由は「休日にまで会社の人と関わりたくない」「気を使うだけでリフレッシュにならない」といった声によるものです。運動会やバーベキュー大会などのレクリエーションも同様ですが、価値観が多様化した現代では、プライベートな時間の侵害と捉える人が多くなっています。特に若い世代では、会社の同僚との私的な交流よりも、家族や友人との時間を重視する傾向が強くなっています。
レジャー施設の優待券も、利用できる施設が限定的で利便性に欠けることが問題視されています。オフィスコンビニについても、ある程度の市街地であれば、近隣に普通のコンビニがあることも多く、品ぞろえ含め外部の方が便利なこともあるため、地域特性上、敷地内に売店が必要な工場などを除き、会社として備える必要性が低くなっているケースもあります。
託児所・育児支援については、子育て世代には非常に重要ですが、独身者や子どものいない世帯には直接的なメリットがないため、公平性に欠けるとの意見もあります。また、オフィス近くまで子連れで出勤することはハードルが高いため、企業内託児所を提供している企業は限定的です。ただ、最近の育児支援関連の法改正を受け、企業でも保育に関連する支援を従業員に提供することが求められているため、何らかの形で支援していく方向性は変わらないでしょう。
その他、前の章でも見ていただいたように手続きが煩雑な制度も敬遠される傾向にあります。
現代の従業員は、使いやすさと実用性を重視しており、形式的な福利厚生よりも実際の生活に役立つ制度を求めているのです。
4.効果的な福利厚生の見直し方法
福利厚生制度を見直す際は、やみくもに制度を削減するのではなく、戦略的なアプローチが重要です。従業員満足度を維持しながらコスト効率を高めるためには、データに基づいた判断と計画的な制度設計が欠かせません。
ここでは、実際に多くの企業で成果を上げている見直し方法を紹介します。
4-1 従業員のニーズ把握
制度見直しの第一歩は、従業員のニーズを正確に把握することです。
定期的なアンケート調査を実施し、「本当に必要な福利厚生は何か」「不要だと思う制度はあるか」など率直な声を集めましょう。
質問を具体的にし、匿名回答を可能にするなど本音を引き出す工夫が重要です。年代別、職種別、家族構成別にニーズを分析することで、より細やかな制度設計が可能になります。
また、現在提供している各制度の利用状況データも詳細に分析し、利用実績が低いものは見直しや廃止の候補として検討します。
4-2 コストパフォーマンスの高い制度の導入
限られた予算で最大の効果を得るため、従業員満足度が高く、比較的低コストの制度を優先的に採用しましょう。
コストパフォーマンスの高い福利厚生制度の例
- 食事補助:社員食堂、食事代補助、無料ドリンク等
- 住宅補助:住宅手当、家賃補助
- リフレッシュ休暇:特別休暇、長期休暇取得推奨
- 健康増進支援:人間ドック補助、スポーツクラブ法人会員
- 選択型制度:カフェテリアプラン、福利厚生代行サービス
食事補助は従業員の生活費負担を直接軽減し、健康維持にも役立つため満足度が高い制度です。
住宅補助も特に都市部では高い効果を発揮し、人材を確保する競争力の向上に直結します。ただし、その一環として社宅や寮を提供する場合は、自社施設を保有すると維持管理のコストがかさんだりすることもありますので、注意が必要です。最近では企業で福利厚生施設を保有するケースは少なくなってきています。
従業員が自分に合った福利厚生を選択できるカフェテリアプラン型の制度なら、多様なニーズに効率的に対応できます。自社での多様なメニュー提供が困難な場合は、福利厚生代行サービスの活用により、低コストで幅広いメニューを提供することも可能です。
5.賃上げと福利厚生の充実はどちらが良い?

結局、「福利厚生はいらないから賃上げで還元してほしい」という声には、どのように答えるべきでしょうか。最初の「福利厚生が『いらない』と言われる理由」の章で見ていただいた通り、賃上げか福利厚生かという二者択一で考えてしまうのには、かなり問題があります。
5-1 賃上げのメリット
賃上げの最大のメリットは従業員の手取り額が直接増えることです。
生活水準の向上や将来への備えが可能になり、物価上昇下では購買力の維持にも直結します。給与水準が競合より高ければ、人材流出防止や採用力向上にもつながるはずです。
特に若い世代では、自由に使えるお金が増えることへの満足度が高く、モチベーション向上に直結しやすい傾向があります。また、賃上げは成果や能力に応じて差をつけることで、従業員のパフォーマンス向上を促す効果も期待できます。
同業他社や地域内で高水準の賃金を提示することで、人材獲得の場面でも、優位に立つことができるでしょう。
一方で、賃上げは固定費の恒常的増加となるため、業績悪化時のリスクが大きくなります。また、賃上げの額によっては税金や社会保険料で相殺されてしまい、従業員の手取りがほとんど増えないどころか、場合によっては下がってしまう場合もあります。
企業にとっては人件費負担が重くなり、経営の柔軟性を損なう可能性もあることを考慮する必要があります。
さらに、昨今の賃上げ事情を鑑みると、一度賃上げしたらそれを下げることはかなりの困難を伴ううえ、毎年のように引き上げられる同業他社、または地域内平均の賃金額以上を維持しなければ、人材獲得競争で優位性を保つことができません。
5-2 福利厚生を充実させるメリット
近年「第3の賃上げ」とも呼ばれる福利厚生の充実が注目されています。昇給やベースアップなどの賃金アップではなく、手当などの福利厚生を充実させることで、従業員の実際の手取りを増やす施策を指します。
福利厚生として提供すれば非課税で受け取れる場合が多く、同じ企業負担額でも従業員により大きなメリットを提供できます。
また、賃上げと違って経営状況に応じて内容や予算を調整しやすく、健康増進策などでは生産性向上といったプラスアルファの効果も期待できます。企業独自の休暇制度やユニークな手当などは、福利厚生の目玉として、対外的アピールをすることで話題になることもあります。
就職・転職活動時に福利厚生を重視する人は8割以上にのぼり、優秀な人材を惹きつける要素にもなるのです。
福利厚生は、基本給が低い傾向にある新入社員、若手社員でも恩恵を受けやすい制度です。休暇制度は若手社員であっても要件を満たせば利用できますし、通勤手当・家賃補助などは実質的な従業員の手取り額面を増やす制度です。福利厚生を必要に応じ拡充することで、賃上げでカバーできない偏りを少なくしたり、必要な社員への支援を厚くしたりすることもできます。
デメリットとしては、福利厚生関連の制度が増えるため、運営の手間が増えることがあります。
さまざまな制度を導入すればするほど申請受付や給付など運用の手間がかかることはもちろん、ユニークな制度でも一定の期間で見直しや改善が求められます。
BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)として、運用をある程度アウトソーシング会社へ委託することも可能ですが、その場合にはアウトソーシング費用がかかるのが悩ましいところです。
5-3 結局どちらがいいのか
賃上げと福利厚生の拡充は、どちらにもメリット・デメリットがあり、福利厚生をなくして賃上げだけでいいとは言い切れません。
ただし、賃上げをまったくしないのも、結局は人材獲得の場面での競争力を失うことになりますので、同業他社または地域の水準に合わせていくことは必要最低限といえます。
そのうえで、法定外福利厚生を上手に拡充し、企業の従業員に対する思いをアピールし、差別化を図っていくことが今後求められていくのではないでしょうか。
6.まとめ
「福利厚生はいらない」という声の背景には、制度の形骸化やコストに見合わない効果といった課題があります。特に従来型の福利厚生制度の多くは、個人向けサービスの充実や働き方の変化など、時代の移り変わりとともに魅力が薄れ「時代遅れ」と評価される場面が増えています。
しかし、これは福利厚生制度そのものが不要ということではありません。重要なのは、時代に合った制度へのアップデートと、従業員の多様なニーズに応える柔軟性です。
成功する福利厚生制度の共通点は、従業員の実際のライフスタイルに寄り添い、使いやすく実用性の高い内容であることです。社員旅行のような画一的な制度ではなく、食事補助や住宅手当のように日常生活に直接メリットをもたらす制度が高く評価される傾向にあります。
賃上げと福利厚生の充実は二者択一ではなく、両立すべきものです。
企業は自社の経営環境と従業員の声を踏まえ、最適なバランスで推進することで、従業員に選ばれ持続的に成長する好循環を生み出すことができるでしょう。定期的な見直しを行いながら時代の変化に対応し続けることが、真に価値のある福利厚生制度の構築につながります。
なお、福利厚生制度の見直しや時代に合った制度設計をご検討の場合は、福利厚生のトータルソリューションを提供するイーウェルにご相談ください。パッケージ型福利厚生サービス「WELBOX」をはじめ、従業員ニーズの把握から効果的な制度設計まで、企業の課題に応じた最適な福利厚生制度の構築をサポートし、従業員満足度の向上と企業の競争力強化を実現する包括的なソリューションをご提案いたします。
充実した福利厚生を目指すなら「WELBOX」
介護・育児・自己啓発・健康増進・旅行やエンターテイメントなど、多彩なメニューがパッケージとなっている福利厚生サービスです。
従業員のライフスタイル・ライフステージに応じて、メニューを選択しご利用いただくことが可能です。
関連記事
Related article
おすすめ記事
Recommend
















